中国は、宴会文化の発達した国です。会食といえば大勢で円卓を囲み、酒を酌み交わす。趣向を凝らした料理で客人をもてなし、共に盛り上がる。日本で「中華」「宴会」と検索すると、なぜか飲み放題がずらずら出てきてしまうのですが、本場の宴会はそんなものじゃありません。え?そんなことするの?そんなことまで考えたの!という驚きと感動がそこにあります。
歴史を遡ってみれば、王道の接待系なら、唐代(618~907)の役人が出世したときに開く「焼尾宴」。妄想系なら、清代(1636~1912)の人気小説「紅楼夢」の料理を再現した「紅楼宴」。食材縛りなら、上海蟹尽くしの「大闸蟹宴」。さらに地域縛りが入れば、洛陽で汁物だけ出す「水席」なんてものもあります。

そう、中国の宴会料理で私たちを待っているのは、目に舌に感動を呼ぶおもてなし。そこでこの「宴会シリーズ」では、そんな中国的宴会を掘り下げてみたいと思います。まず1回目は「呉師傳揚州名菜宴」、揚州料理の宴会です。
●宴会はいつも「あの人の本気が食べたい」から始まる
今回揚州宴を開いたのは、江南料理を得意とする「JASMINE憶江南」。店名に「憶江南(江南を想う)」とある通り、JASMINE各店の中でも、江南地方の料理をより深く味わえる店がこちらです。

そのJASMINEグループに「揚州出身の呉林という料理人が入った」と聞いたのは少し前の話。呉さんはそれまで函館のホテルに勤務していたそうですが、ある日、JASMINEという店を知り、東京に面接に行くことを決意。その理由がなんと「コノ店、自分ノ故郷ノ料理ダシテタ」からだという…!
 呉林さん
呉林さん
聞けば彼は、中国でも選ばれし特一級厨師・居長龍(きょ ちょうりゅう)氏の兄弟弟子。居長龍といえば、日本の中国料理界に多大な影響を与えた揚州料理人として業界では知られる方。その薫陶を受けた彼ですから、やはり腕は確かだったんですね。
「彼が作るランチや賄いがいいんですよ。おかげで広尾店の売上も上がりました。だから一度、呉さんが作る揚州料理のコースを僕自身が食べてみたいんです。宴会しましょう!」
そう話を持ちかけてくれたのは、JASMINEグループ総料理長の山口氏。こうして、ある秋の日に、揚州宴が開かれる運びとなったのです。(結果的には、山口さん自身も厨房に入ったのですが…!)。
●ところで揚州ってどこですか?
そんな呉さんの故郷・揚州市は、江蘇省の長江沿いにある歴史ある都市。唐代には日本の遣唐使の中継地となり、清代には塩の貿易により揚州商人が巨額の財を成した場所でもあります。
また、鑑真が日本に渡る前、住職を勤めていたのは揚州の大明寺。とはいえ「そんな歴史は頭に入らない」というアナタ。揚州炒飯といえば興味を持っていただけるのではないでしょうか。そう、あの五目炒飯です。

また、皇帝をもてなした「満漢全席」も、実は揚州が発祥です。象の鼻、らくだのコブ、蛇、つばめの巣、ふかひれなど、山海の珍味を贅沢に使った「満漢全席」は、揚州商人が時の皇帝、清代の乾隆帝(グルメで有名)をもてなすために、漢族と満州族、両方の料理を取り入れて献上したのがその始まり。そんな歴史があるからでしょうか、揚州大学には、中国の大学で初めて設立された料理学部もあるのです。
●メニューはこちら!気分はいにしえの揚州へ――
では、現代の揚州人が繰り出す宴会料理はどんなものなのでしょうか。伝統的な宴会料理の形式に則って作られた菜譜(メニュー)がこちら。
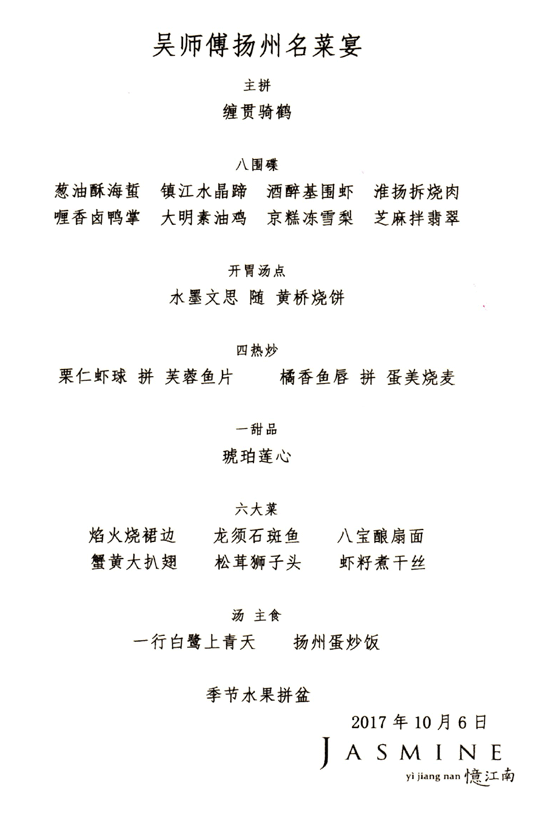
呉師傳揚州名菜宴(メニュー)
漢字から推測できる部分もあると思いますが、一部は中華に詳しい方でも、理解しにくい料理があるかもしれません。ぜひ料理名から料理をイメージしつつ、続くお料理をお楽しみください。
※料理名は日本の漢字表記(中国語表記(簡体字))の順に記しています。
●1皿目に「食べられる絵」が登場!
出ました…!まず一品目は、拼盤(拼盘:ピンパン)です。拼盤とは中国の伝統的な飾り前菜。お客さまを迎えるにあたり「まず目を楽しませる料理を」というおもてなしの心がここにあります。
 主拼:纏貫騎鶴(缠贯骑鹤)
主拼:纏貫騎鶴(缠贯骑鹤)
しかし、心が込められ、キレイなだけじゃないのが中国料理の深いところ。中国の料理は時に文学的で、遡ること南北朝時代(西暦500年前後)、小説『吴蜀人』の一節より「缠贯骑鹤(纏貫騎鶴:腰に大金を巻き付け、鶴に乗って揚州に行く)」という話がこの拼盤のモチーフになっています。ざっくり言うと、
「君はどんな夢を叶えたい?」
「揚州の長官になりたい」
「お金持ちになりたい」
「鶴に乗りたい」
「腰に10万両を巻き付け、鶴に乗って揚州に行けば全部叶うじゃないか!」
というストーリーがここに。そう、いにしえの揚州は、豊かな都市であり、人々の憧れの地。呉さんは、往年の揚州がどれほど魅力的な場所だったか、宴会の冒頭で伝えるとともに、卓を囲んだ皆の商売繁盛をこの料理に込めていたのです。
●主役を引き立て、存在感も放つ八仙人
そして、拼盤(ピンパン)を取り囲むように並んだ8皿の前菜が「八囲碟(八围碟)」。八=八つ、围=囲む、碟=小皿で、これらは主拼(メインの拼盤)を囲む8つの小皿を意味します。
八は末広がりで縁起のいい数字。一般的な日本の中国料理のコースの場合、前菜からデザートまで8品という構成はよくありますが、ここでは前菜のみで8品です。中国式宴会、おそるべし。
 鎮江水晶蹄(镇江水晶蹄)
鎮江水晶蹄(镇江水晶蹄)
豚脚肉の煮凝り
鎮江水晶蹄(ヂェンジャンシュイジンティ)は、長江を隔て、揚州の南にある鎮江市の名物。蹄に近い豚の脚の肉を煮凝り状に固めたもので、鎮江肴肉(ヂェンジャンヤオロウ)とも呼ばれます。
鎮江は鎮江香醋、黄色いキャップの黒酢で有名な都市で、提供にはもちろん黒酢を添えて。ハムっぽさもありつつ、よりゼラチン質が感じられる食感で、控えめな塩味がたまりません。
 酒酔基囲蝦(酒酔基围虾)
酒酔基囲蝦(酒酔基围虾)
車海老の紹興酒漬け
江南地方は、紹興酒をはじめとする黄酒(ホアンジュウ:日本酒と同じくらいの度数の醸造酒。主にもち米が原料)の産地。今の季節、この紹興酒を使って漬ける料理の代表格が上海蟹を漬けた酔蟹(酔っ払い蟹)ですが、同じ漬け地で活けの海老も仕込めます。
臭み消しのために生姜や香辛料を加え、澄んだ甘味のために氷砂糖を使って生のまま漬け込めば、見事トロトロになった海老の身に…!
 葱油酥海蜇
葱油酥海蜇
花咲くらげの葱油風味
前菜の定番・くらげは盛り付けに華やかさのでる花咲くらげを使用。葱油の香りを生かしたさっぱりとした前菜です。
 淮揚拆焼肉(淮扬拆烧肉)
淮揚拆焼肉(淮扬拆烧肉)
揚州式煮豚
醤油味で上品に煮込まれた、揚州式の煮豚。揚州料理は淮揚菜(わいようさい/ファイヤンツァイ)とも称されるため、料理名を5文字に揃える意味も兼ねて、この名を冠しています。
料理名にある「拆」とは、解体する、バラバラにするという意味。推測ではありますが「豚を一頭解体し、各部位を解体した際にこの料理も作られていたのでこの名前が付いたのではないでしょうか」と山口総料理長。中国語では「焼」=「煮る」調理法なので、広東地方のように窯で焼く叉焼(チャーシュー)ではなく、煮豚というのもポイントです。
 喱香滷鴨掌(喱香卤鸭掌)
喱香滷鴨掌(喱香卤鸭掌)
アヒルの水かきの滷水煮込み
中国人は、鳥獣家禽を食べるとき、よく動く部位を好む人が多いです。総じてこうした部位は柔らかくも弾力のある食感で、コラーゲンが豊富。鸭掌(アヒルの水かき)もそうした部位ひとつです。
カレー味にしたのは味と色のバリエーションをつけるため。いつまでも齧り、しゃぶりつきたくなるつまみ系前菜です。
 大明素油鶏(大明素油鸡)
大明素油鶏(大明素油鸡)
湯葉の鶏もどき
素鶏は上海の素食(精進料理)でよく使われる食材。大豆などの植物性たんぱく質で作られており、名前の通り、鶏むね肉に似せている食材です。
中国の都市部ではスーパーなどでも買うことができますが、ここで出されたのは湯葉を使った手作り。鶏ベースのスープで、上品にうまみを煮含めてあります。
 京糕凍雪梨(京糕冻雪梨)
京糕凍雪梨(京糕冻雪梨)
山査子(さんざし)と梨の羊羹
京糕とは北京風のケーキというニュアンス(京=北京)。山査子と梨を2層にして寒天で固めた、美しい羊羹です。山査子の風味を生かしたほのかな甘酸っぱさと、梨のさっぱりとした風味が口中でひとつになる、品の良い甜品。これ単品で売り出してほしい、季節の菓子でした。
 芝麻拌翡翠
芝麻拌翡翠
春菊の茎の胡麻和え
なんと茎だけ!春菊の茎を集めた、ありそうでない冷菜です。昨今はパクチーサラダが人気ですが、それを彷彿とさせつつ、ゴマ香る品のよい和え物に。なぜ茎だけか?という答えはのちほど明らかに。
●僧侶が発明、超絶技巧の豆腐料理
 開胃湯点(开胃汤点):水墨文思 随 黄橋焼餅(水墨文思 随 黄桥烧饼)
開胃湯点(开胃汤点):水墨文思 随 黄橋焼餅(水墨文思 随 黄桥烧饼)
胃を開くスープと点心:文思豆腐と焼き点心
開胃とは、文字通り「胃袋を開く」ということ。前菜の後はスープ(湯)と点心(点)で、さあ胃袋を開こう!という料理が登場します。
まるで糸のように切られた白い物体は豆腐。これぞ揚州名菜「文思(ウェンスー)豆腐」で、清朝乾隆帝の時代に、僧侶の文思が生み出した、有名な精進料理です。
豆腐を縦に切り、中華包丁で倒し、さらに横に包丁を入れ、目指すはところは毛髪の細さ。それを透明なスープに放てば、まるで水墨画のような景色が現れます。(プロセスは有名番組「舌尖上的中国(舌の上の中国)」にて。
元々は干し椎茸のスープで作っていましたが、今は様々なアレンジがあり、ここでは干し貝柱ベースのスープに、なんとキュウリを濾した汁で翡翠色にアレンジ。ものすごく久しぶりに作ったため、呉さんとしては精度が低い仕上がりだったそうですが、いやはや十分に楽しめました。
また、添えているのはこれまた揚州名物、黄桥烧饼(黄橋焼餅)。焼餅(シャオビン)とは、小麦粉の生地を平べったく焼いたもので、黄橋決戦(1940年、中国共産党と国民党の戦い)で解放軍の兵士に振る舞われたものが由来と言われています。
生地はさくさくとした食感に仕上がる「油酥皮」と、水を練り込んだ「水油皮」を作って合わせるのが特徴。中国ハム、葱、胡麻の餡を包んだ、食感豊かな点心です。
●温かい料理がガップリ四つ巴
胃袋を開いていよいよ料理受け入れOKになったら、いよいよ四熱炒(スールーチャオ)、温かい料理の出番です(マニアックポイント:四熱菜ではなく、ここでは四熱炒でした)。料理は2種類の料理併せ盛りスタイルで登場です。
 四熱炒:栗仁蝦球 拼 芙蓉魚片(栗仁虾球 拼 芙蓉鱼片)
四熱炒:栗仁蝦球 拼 芙蓉魚片(栗仁虾球 拼 芙蓉鱼片)
四つの温かい料理:栗入り揚げエビ団子+魚の卵白炒め
ピンポン玉ほどの大きさの揚げ団子は、秋の味覚、栗を加えたエビ団子。表面に細切りのじゃがいもをまぶして香ばしく揚げており、上品な団子の風味がいい感じにスナッキーでたまりません。
「芙蓉」とは、白い芙蓉の花のように、白くふわっとした食感の料理に使われる言葉。「魚片(ユイピィェン)」とは魚の切り身のことですが、ここではすり身にした白身魚にスープ、卵白、片栗粉を混ぜ、気泡も上がらないほど低温の油で静かに揚げ、至極滑らかで、舌の上でふわりと消える魚片を再構築しています。
 四熱炒:橘香魚唇 拼 蛋美焼麦(橘香鱼唇 拼 蛋美烧麦)
四熱炒:橘香魚唇 拼 蛋美焼麦(橘香鱼唇 拼 蛋美烧麦)
四つの温かい料理:柑橘の香りの鮫の縁側煮込み+シュウマイ
魚唇(ユイチェン)は鮫の縁側で、日本でも流通しているおなじみの食材。フカヒレよりもコラーゲン分が豊富で、とろっとろの食感が楽しめます。なんとこの部位を、呉さんはフレッシュなみかんの皮を入れて煮込みました。片栗粉でとろみをつけてから、みかんの汁を入れ、さらに爽やかさを出したのだとか。
料理の色は、辛さを感じさせないほど少量の豆板醤も加えて鮮やかなみかん色。風味はそれほど強く柑橘香は感じないものの、おだやかにキレがよく仕上がっています。
相い盛りの焼売は、豚肉、エビ、筍、そして砂肝が入った餡。この砂肝が地味にいい仕事をしており、コリッと歯切れのよい食感をプラス。中国ハムで塩気を加えるとともに、幾重にも旨みが重なります。この一皿は、古典的な料理の印象を残しつつも、新しさを感じる料理の取り合わせでした。
●甘くてもデザートに非ず。箸を休めていざ次へ
 一甘品:琥珀蓮心
一甘品:琥珀蓮心
一品甘いもの:蓮の実を詰めた龍眼
ここで料理のアクセントになり、次へと向かう甘い料理が入ります。お碗をひっくり返した形に盛り付けられているのは、龍眼(りゅうがん:ロンイェン)の中に蓮の実を詰めたもの。
薬膳料理の観点からすると、氷砂糖でキレイな味に煮含められた龍眼は、滋養強壮、不眠などに効果のあるもの。ホクホクのハスの実は安心(アンジン:心を落ち着ける)効果があるとされています。
周囲にぐるりとあしらわれているのはみかん。彩りがいいのはもちろん、龍眼の甘さをさっぱりとさせてくれるのがいいですね。
●メイン中のメインが選べない!主役の六大菜

 六大菜:焔火焼裙辺(焔火烧裙辺)
六大菜:焔火焼裙辺(焔火烧裙辺)
六大菜:スッポンのエンペラの豚の腹脂煮込み ブランデーのフランベ
裙辺(チュンビィェン)とはスカートの意味。中国語の料理名をそのまま読むと、スカートを燃やしてしまうようですが、裙辺が食材名になるとスッポンのエンペラを意味します。エンペラはスッポンの甲羅の周りの、ヒラヒラとした部位で、高級乾物としても流通しています。
そのふるふるとしたゼラチン質の塊であるエンペラを、板油、すなわち豚の腹部の厚い板状の脂肪を使って4時間煮込み、深いコクを加えた料理がこちら。提供する前に部屋の明かりを消し、ブランデーで燃やしてから提供するという演出です。
 六大菜:龍須石斑魚(龙须石斑鱼)
六大菜:龍須石斑魚(龙须石斑鱼)
六大菜:龍の髭をはやしたハタ
続くは食卓の華!五島列島は「林鮮魚店」直送のスジアラに、錦糸卵、まこもたけ、戻した干し椎茸、中国ハムの千切り、金針菜をあしらった魚の蒸しものが登場。
何気なく載せられているように見えて、実は「具を並べる順番も大事です」と呉さん。例えば、ハムを尾に近いところに並べているのは、塩気が強い食材であるため。全体をしっかり混ぜてからいただくと、確かに塩気のバランスがちょうどいいのです。彩りだけでなく、味も考えて配色しているんですね。
 六大菜:八宝醸扇面(八宝酿扇面)
六大菜:八宝醸扇面(八宝酿扇面)
六大菜:扇形の八宝豆腐
淡い色合い、すっきりとした風味の、揚州料理らしい一品。自家製豆腐の上にあしらわれているのは、干し椎茸と銀杏で描かれた梅の木です。しかし「銀杏ってちょっと色と質感が違うよね?」と思ったあなた。これ、よーく見ると、銀杏の表面を削り、さらに上部を花形に細工しているんです。銀杏の実って、外側が薄い黄緑、内側が濃い黄緑色なんですね。
ちなみに揚州の名産品といえば揚州三把刀(ヤンヂョウサンバーダオ)。これは包丁、髪を切るためのハサミ、修脚(足の手入れのための刃物)の三種の刃物のこと。そして揚州料理もまた、刀工技術が優れているで有名です。グリンピースを置くのではなく、季節の銀杏を細工されていたことに、揚州人の魂を感じました。
 六大菜:蟹黄大扒翅
六大菜:蟹黄大扒翅
六大菜:ふかひれの上海蟹味噌煮込み
中国の秋の味覚、上海蟹(大闸蟹)の味噌を使ったふかひれの煮込みです。一般的なコースですと、この料理がメイン中のメインになりそうですが、他の料理も凄すぎて、もはやどれがメインだなんて選べない…!
材料となる上海蟹が水揚げされるのは、揚州市と上海市の間にある陽澄湖(ようちょうこ)や太湖など。特に陽澄湖産が有名なのは、蘇州市がブランドを守っていることもありますが、蟹が産卵前に長江の河口まで川を上り、再び湖まで戻ってくるのにちょうどよい距離であり、よく鍛えらえた蟹であることが大きな要因と言われています。
 六大菜:松茸獅子頭(松茸狮子头)
六大菜:松茸獅子頭(松茸狮子头)
六大菜:大きな肉団子 松茸のせ
揚州料理を代表する名菜、獅子頭(シーズトウ)。ひと言でいうと大きな肉団子で、中はふわっふわ。どっしりとした見た目とは裏腹に、箸を入れれば待って待って!!と言う間もなく肉汁がほとばしる、ライブ感たっぷりの料理です。
一般的な獅子頭は真ん丸のボール形のところ、9人前を1つの大きな塊としたため、ここではやや平べったい形状に。一度揚げ焼きにして表面を固めたら、今度じっくりと蒸し上げ、中まで火を通してから餡を絡めます。
餡のベースになる煮込みスープの製法が独特で、水と醤油に豚軟骨を入れて煮るのが呉さん流。軟骨を入れることで、澄んだスープに太いコクが生まれるのだそう。獅子頭の上に放射線状に並べてあるのは松茸。周囲には豆苗の炒めを配して、花のように仕立てました。
 六大菜:蝦子煮干絲(虾子煮干丝)
六大菜:蝦子煮干絲(虾子煮干丝)
六大菜:押し豆腐の川蝦の卵風味煮込み
押し豆腐の塊を細く均一に切り、さらに滑らかな食感に仕立てるのが決め手となる料理。丁寧に下処理された押し豆腐は、されていなものとはまったく別物です。「押し豆腐って、ゾワゾワしてあまり好きじゃない」という方も、同店の押し豆腐をいただけば、柔かいのにほどよい歯ごたえのある、この食感に驚くことでしょう。
具は金華ハム、小エビ、筍など、いずれも旨みの出る食材。白濁した煮汁は上湯がベース。上質なス―プで干絲をじっくり煮込むことで、干絲はスープの旨みを吸い、スープには食材の旨みが移ります。揚州料理の定番中の定番。清の乾隆帝時代に生まれた料理です。
●揚州炒飯が揚州炒飯たる理由とは
 揚州蛋炒飯(扬州蛋炒饭)
揚州蛋炒飯(扬州蛋炒饭)
揚州炒飯
揚州炒飯の定義は、使用する材料に縛りがあると思われているところがありますが、実は決定的な違いはプロセスにあるという発見がここに。
その作り方は、まず卵をたっぷりの油で炒め、さらに具を炒めたものを用意。その後、鍋にごはんと先ほどの卵を入れて炒飯を作り、あらかじめ炒めておいた具を加えて煽るというもの。
「汁気を飛ばしながら、米と具を焼いて、香ばしい香りを出していくイメージですね。だから、広東のようなパラッパラの炒飯じゃないんです。むしろしっとり系の焼き飯ですね」と話してくれたのは山口総料理長。
参考までに、2002年に揚州市烹飪協会で規定している材料は、ナマコ、鶏もも肉、中華ハム、ほたて、えび、しいたけ、筍、青豆。作り方には諸説ありますので、その点はご留意を。
 一行白鷺上青天(一行白鹭上青天)
一行白鷺上青天(一行白鹭上青天)
青菜と魚肉団子入り澄ましスープ
白鷺が青空に列をなして飛んでいくという料理名の通り、上湯の中に鷺に見立てた団子が美しい一品。唐代の詩人で、詩聖と称される杜甫の絶句の一節を料理名に引用しています。
魚団子は中国各地にありますが、魚に片栗粉や卵白などを加えないで作るのが揚州式。団子の弾力の決め手となるのは塩で、塩をしっかり入れ、さらに水も加えて魚肉を練っていくと、次第ににぷりんとした弾力が生まれてくるのだそう。その後、団子状に整えたら、水に放って塩気を抜くというプロセスが独特です。
現地では、魚は淡水魚の鰱魚(れんぎょ:リィエンユィ)を使うのが一般的。野菜は芦蒿(ルーハオ)、芹とアスパラを足して割ったような香りの良い野菜を使いますが、ここでは鯛と春菊の葉で代用しています。
 季節水菓拼盆(季节水菓拼盆)
季節水菓拼盆(季节水菓拼盆)
パイナップルタワー
最後は塔を模したパイナップルで〆。日本に仏教を伝えた鑑真が住職を務めた大明寺の塔でしょうか。刀工技術が自慢の揚州料理人らしく、呉さんは最後まで見事な造形を見せてくれました。
●様式と料理を通じて、中国の歴史や文化に触れる宴会でした
緩急をつけるどころか、すべてが気合い十分。めくるめく揚州宴は、怒涛の25品で幕を閉じました。中国の宴会料理は、ひとつの様式があるからこそ深さが生まれ、料理を通じて、その先にある歴史や文化を知ることができるからこそ、豊かさがあると改めて感じました。
また、今回は材料を無駄にしない使い方が冴えてましたね。例えば、橘香魚唇(鮫の縁側の煮込み)に生のみかんの皮をたっぷり使ったら、琥珀蓮心(龍眼と蓮の実の蜜煮)の周囲にみかんをあしらい、芝麻拌翡翠(春菊の茎の胡麻和え)で春菊を使ったら、最後のスープで葉を使う。素材の一部だけ使うのではなく、すべてを生かし、無理なく、しかも美しい料理に昇華していました。
なお、乾物を戻し、鎮江水晶蹄を作る以外はすべて当日の仕込みだそう。「僕たちが手伝ったのは、食材を発注したり、豆苗の葉をむしったり、その場で皿を出したりするだけです。仕込みはぜんぶ呉さんがやりました」。そう話してくれたのは山口総料理長。
「これほどすべての仕事をまんべんなくできる料理人はそうそういません。前菜、点心、包丁技、味付け、さらにセンスも含めて、ものすごくバランスがいいんです。それと、なにより料理が好き。ともかく料理が好きなんです。すごく楽しそうに料理していて、終わってからも『ありがとう、ありがとう』とみんなと握手していましたね」。
いやあ、最後にいい話。そんな呉さんの料理をいただけて、私たちも幸せでした!
TEXT & PHOTO 佐藤貴子








![[医食同源]トウモロコシはスープが美味!蓮根、スペアリブと合わせて夏冷え・むくみ対策](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/1_IMG_9376-218x150.jpg)

![葱姜油で香味ドーピング!葱油手撕鶏(チキンの葱生姜まみれ)の作り方&楽しみ方[レシピあり]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1_IMG_4118v3-218x150.jpg)

































![[医食同源]トウモロコシはスープが美味!蓮根、スペアリブと合わせて夏冷え・むくみ対策](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/1_IMG_9376-696x385.jpg)








