揚げ焼きからの、窯でパリッ!専用調理機器で生まれる無二の食感
また、鍋魁(グオクイ)は鉄鍋で煎り焼きした後、釜焼きをするという2段階の焼成工程によって、独特のジャクッ・パリッ・サクッという食感を生み出している。焼成には、鉄鍋と炉が一体になった専用の調理機器を用いており、この機器の製造も軍楽鎮の産業となっていた。
焼き方は、まず丸皿のような鉄鍋にたっぷりと菜種油を入れ、成型した鍋魁の生地を入れて両面を返しながらこんがりと揚げ焼きにする。

そこであらかた火が通ったら、今度は炙り焼きだ。炉の中に作られたドーナツ状の窯に、鍋魁を立てて並べ、遠火で焼き上げるのだ。ここでじっくり焼くと油が落ち、さらに表面がパリパリに焼き上がる。

簡単そうに見えて、この焼成工程も意外と難しい。最初は数個から始めるが、ベテランが焼き上げる数は一度に14個。私にとって、菜種油の入った鉄鍋は重く熱く、慣れない長尺バーベキュートングを使って鍋魁を焼いたのち、窯に並べていくのは成型よりもずっと難易度が高かった。

それに加えて、主たる熱源であるコークスには苦しめられた。成都市や重慶市の繁華街では電熱器を使っているところが主流だが、軍楽鎮は良くも悪くもオールドスタイルなのだ。
炉で赤赤と燃える様を眺めるぶんには暖炉の火のようで心惹かれるのだが、ひとたび風が吹いて煙を吸い込むともう大変。地元の皆はケロリとしていたが、私は咳が止まらなくなり、これには体力を消耗した。

再び鍋魁を食べに行ける日を夢見て
こうして軍楽鎮の店に通い、3食賄いつきの8日間。成都市街に続く街道に面した半露店で、往来する農業用の赤い小型トラックや、豚がぎっしり詰まれた大型トラックなどを眺めながら、バン!バン!と鍋魁の生地を打ち付け成型するという経験は、ふと我に返ると夢のようでもあり、第二の人生を生きているようでもあった。


聞けば、ここで修行している人たちののほとんどは、ここから20キロ圏内に住んでいた。
「今は塗装の仕事をしているけど、スプレーを吸い込むと身体によくないから、食の仕事を覚えておこうかと思って」という塗装職人。「今は料理人をやっているけど、あれこれ作るのは大変だからこれ1本で勝負したいんだ」という料理人。「福建省でお姉さんと店を開きたいの」という子もいた。もし自分がここで生まれ育ったら、どんな人生を送っただろう。

そろそろ修行も終わろうという頃、軍楽鎮政府の皆さんが、点心師とライターが揃って修行と取材に来たということで、丁寧に食堂に招待にしてくれ、鍋魁の工場を見学させてくれた。
工場といっても、中で職人が手作りしているため、冷凍するかしないかの違いしかない。「冷凍品を加熱したものです」といって出された鍋魁は、そうとは思えないくらい香り高くクリスピーな食感。工場の担当者は「いずれ国内線の機内食にしたい」という夢があるという。
こんな鍋魁が四川航空の機内食で出たら、かなりテンションが上がりそうだ。また、このクオリティの鍋魁が日本に輸出できるようになれば、評判になるに違いない。


その一方で、鍋魁はあの麺打ちパフォーマンスを見ることで、さらにおいしく感じる要素がある。周先生のような職人を呼び、日本でイベントができたらなあ…などと食べながら夢想してしまった。
帰国して、現地の巨大な鉄板を丸型の鉄製餃子鍋、コークスを燃やす炉をオーブンに替えて、さっそく東京で再現を試みた。しかし、老麺も違えば粉も異なり、調理器具も違うとなると、そこそこ見た目は似ていても、まったく同じようになるはずがない。坪井ちゃんも家で試作を重ねたというが、自分が納得できるところに至るまでには時間がかかったそうだ。
食は、土地と人に育まれた味がある。そう思うと、いつかまた、軍楽鎮まで鍋魁を食べに行きたいと思わずにはいられない。
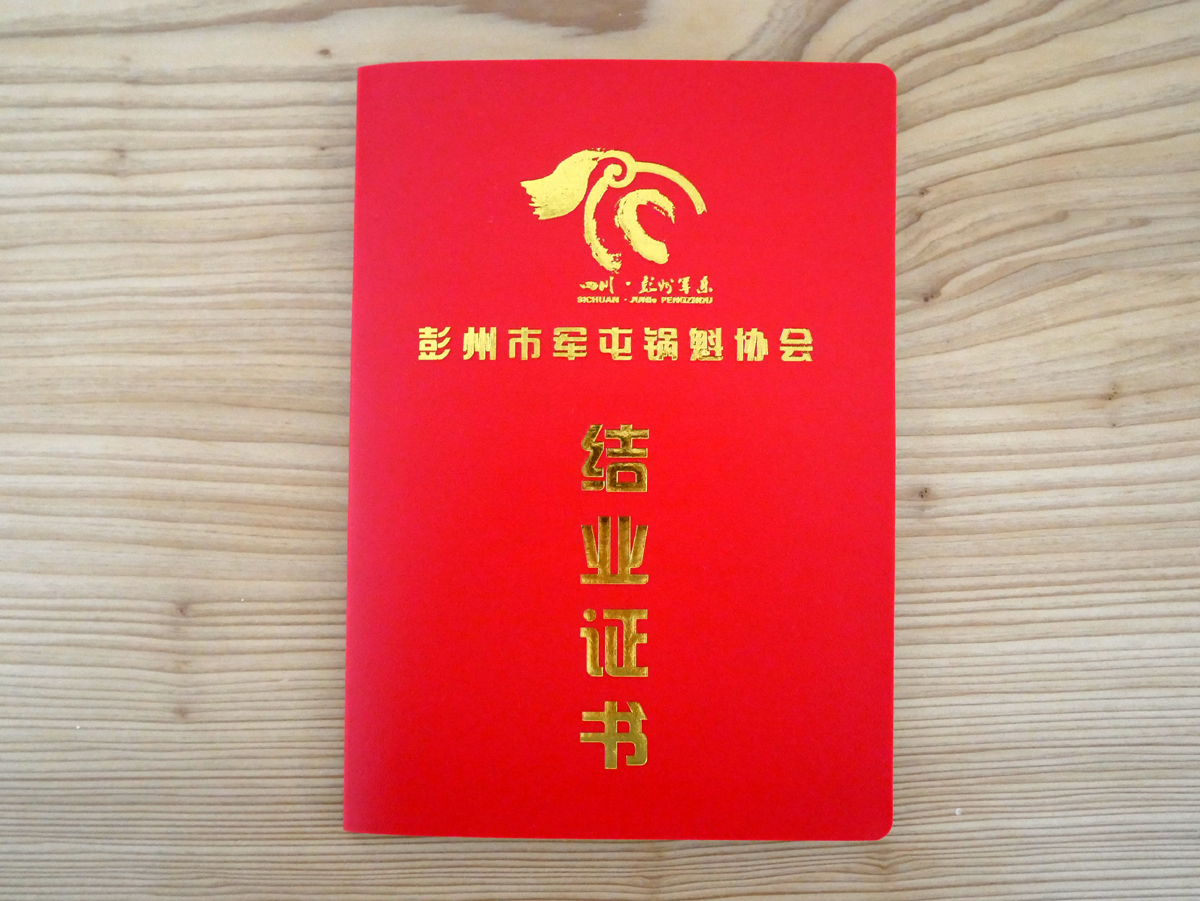
TEXT & PHOTO サトタカ(佐藤貴子)








![[医食同源]トウモロコシはスープが美味!蓮根、スペアリブと合わせて夏冷え・むくみ対策](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/1_IMG_9376-218x150.jpg)

![葱姜油で香味ドーピング!葱油手撕鶏(チキンの葱生姜まみれ)の作り方&楽しみ方[レシピあり]](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/04/1_IMG_4118v3-218x150.jpg)



























![中華の真髄は郷土料理にあり!今注目される台州料理総まとめ[後編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/08/28_baishuiyang-218x150.jpg)
![2023年、中国の食のトレンドに!いま食べるべき台州料理とは?[前編]山口祐介の江南食巡り⑧](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2023/07/IMG_9200-218x150.jpg)







![[医食同源]トウモロコシはスープが美味!蓮根、スペアリブと合わせて夏冷え・むくみ対策](https://80c.jp/wordpress/wp-content/uploads/2024/07/1_IMG_9376-696x385.jpg)








